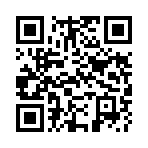日経 11月18日
2024年11月18日

2024年11月18日(月)
・電力大手やJR東日本 <9020> [終値2096.0円]
2024年度中に送配電網をドローンの航路として実用化する。
送電線上空を航行する運航管理システムを近く販売し、
電線や鉄塔などの点検を皮切りに電子商取引(EC)の物流や災害状況の確認など用途を広げる。
利用できる電力大手の送配電線は全国に130万キロメートル超あり、
ドローンの産業利用が本格化する。
・送電網上の航路の設計や運航システムの開発を担う
グリッドスカイウェイ有限責任事業組合(東京・港)が25年3月までにシステムを販売する。
機体の貸し出しも組み合わせ、定額課金型のサービスとして収益化を目指す。
同組合には東京電力パワーグリッド(PG) <9501> [終値580.6円]など送配電大手9社のほか、
JR東日本 <9020> [終値2096.0円]、日立製作所 <6501> [終値3951円]などが出資。
送配電会社の了承を得て送電線の上空を飛ばす。
送電線をドローン航路に使うのは世界でも珍しい。
国土が狭く山間部も多い日本は位置などのデータがあり、
周辺に飛行物が少ない送電網を使った方がドローンの航路計画を立てやすい。
航路は送電線や樹木と一定の距離を保つように設定。
運行管理者が遠隔で常時監視し安全に万全を期す。
まずは電力インフラの点検で航路を活用する。
・インプレス総合研究所によると、日本のドローンサービス市場は
28年度に5154億円と23年度比で2.5倍に増える見通し。
物流のドローン活用は過疎地や災害時の支援物資の輸送などの面で期待が大きい。
セイノーHD <9076> [終値2483.5円]などは
北海道の一部地域や山梨県でドローン配送を実施している。
・日経新聞社とテレビ東京 <9413> [終値2970円]11/15~17に定例世論調査を実施。
石破茂内閣の支持率は46%で、前回10月の政権発足を受けた緊急世論調査から5ポイント下落。
内閣を「支持しない」は9ポイント上昇し、46%となった。
内閣を支持しない理由は「自民党中心の内閣だから」が36%で最多となった。
第2次石破内閣の顔ぶれを「評価する」と答えた人は25%、「評価しない」は55%。
政党支持率は自民党30%、立憲民主党16%、国民民主党11%で、
特定の支持政党を持たない無党派層は19%。
10月はそれぞれ41%、11%、1%、29%で、国民民主は10ポイント上がった。
調査は日経リサーチが15~17日に全国の18歳以上の男女に携帯電話も含めて
乱数番号(RDD方式)による電話で実施し800件の回答を得た。回答率は37.4%だった。
・異常気象が人類を脅かす「プラス2度」の世界が近づく。
地球の平均気温は観測記録を更新し続けている。
11/11に国連気候変動枠組み条約第29回締約国会議(COP29)が始まったものの、
国際社会の足並みはそろわない。
米国では脱炭素に後ろ向きなトランプ氏が再び大統領に就く。
温暖化が進んだ未来の日本は巨大台風の襲来や極端な豪雨が増えると科学者は予測する。
24年は観測史上、最も暑い年になる。
10月までの地球の平均気温は産業革命以前より1.6度高い。
国際社会が目指す1.5度以内という目標は遠のく。
異常気象がさらに深刻になる2度上昇も現実味を帯びる。
日本の洪水リスクは2度上昇で2倍に増す。
海面上昇は沿岸部の住民を不安に陥れ、移住も選択肢になる。
・世界はもっと深刻だ。宅地の水没、水害の多発、干ばつといった
気候変動の災禍で住めなくなる場所は増える。
移住を迫られる人は世界6地域で50年に2億1600万人に膨れ上がると世界銀行は予測する。
太平洋のフィジーにある村「ケナニ」の名は現地語で神が与えた約束の地を意味する。
14年に約150人が海岸沿いから移転してきた。
海面上昇で旧村を襲う高潮は年々、深刻さを増していた。
先進国でも移住は始まっている。
米ワシントン州の太平洋沿岸に位置するクイノールトでは数百人が高台移転を計画する。
海面上昇で海岸線が浸食され、水害を経験した。
5年以内の移転を目指すが遅れている。
金銭負担を理由に移転を望まない人も多い。
気候変動の責任の所在を巡る先進国と途上国の対立が、国際交渉の障壁となっている。
住む場所を追われる人々をどう救うのか。
世界全体で向き合う時期にきている。
・日経新聞社とテレビ東京 <9413> [終値2970円]11/15~17の世論調査で、
国民民主党が自民、公明両党の与党に政策ごとに協力する方針を評価するかどうか聞いた。
「評価する」とした人は67%に上った。
「評価しない」は22%にとどまった。
国民民主は衆院選で若い世代を中心に支持を集めた。
18~39歳の7割超が政策協議を評価した。
自民党支持層に限っても8割近くに達した。
所得税の納付が必要になる「年収103万円の壁」についても尋ねた。
国民民主は所得税の非課税枠を103万円から178万円に引き上げるべきだと主張する。
「手取りを増やすため、非課税枠を178万円に広げるべきだ」と答えたのは38%になった。
非課税枠を178万円に広げる国民民主の提案への賛成意見は若い世代で目立った。
18~39歳は61%で、全世代よりも比率が高まる。
40~50歳代は50%だった。
60歳以上になると国民民主案への支持が23%と低下する。
限定的な非課税枠の拡大への賛成が最多の40%となった。
・国民民主党の支持率が前回10月の調査と比べて10ポイント上昇の11%となった。
2020年9月に現在の国民民主党が結成されて以来、過去最高を記録した。
自民党、立憲民主党に次ぐ3位につけた。
これまでの最高は24年1、2月の4%だった。
男女別の支持で見ると男性が13%、女性が8%だった。
18~39歳の若い世代に限ると、全政党のなかで最も支持を得て25%になった。
全世代の自民党の支持率は30%で前回の調査から11ポイント低下した。
・過去最多の7人が立候補した11/17投開票の兵庫県知事選は、
前知事の斎藤元彦氏が元尼崎市長の稲村和美氏らを破り、返り咲いた。
「勝手連」として集まったスタッフがSNSを駆使し、斎藤氏の訴えなどを拡散した。
パワハラ疑惑などを内部告発された問題で不信任決議を受けた斎藤氏は、
失職した直後から各地の駅前に立ったが、聴衆はまばらだった。
だが、告示後の第一声には数百人が集まり、その後も数は増えた。
攻勢の原動力となったのは、SNSへの投稿を担う約400人のスタッフだ。
「斎藤か斎藤以外か。絶対に負けるわけにはいかない」
「引きずり降ろそうとするいろいろな声や力がある」。
SNSに投稿した写真や動画が次々に拡散された。
斎藤氏のX(旧ツイッター)フォロワー数も9月末の約7万から20万超に増えた。
・日本維新の会は11/17、衆院選を受けた党代表選を告示。
届け出順に吉村洋文共同代表(大阪府知事)、金村龍那衆院議員、空本誠喜衆院議員、
松沢成文参院議員の4人が立候補した。
議席を減らした衆院選の総括や失速する党勢の回復策が争点となる。
12月1日の臨時党大会で投開票する。
・バイデン米大統領と中国の習近平(シー・ジンピン)国家主席は11/16、
訪問先のペルーの首都リマで会談した。
トランプ次期米政権が発足すれば米中対立のさらなる深まりが懸念されるなか、
外交や軍事など幅広い分野での戦略的な対話の継続で一致した。
米中は23年の首脳会談以降、軍事や外交、通商といった幅広い分野で対話を重ねてきた。
台湾海峡や南シナ海で米中両軍がにらみ合う状況になっても衝突まで発展しなかったのは、
首脳間を含む意思疎通が続いていたからだとの見方は多い。
・バイデン米大統領と中国の習近平(シー・ジンピン)国家主席は11/16、
ペルーの首都リマで開いた首脳会談で、核兵器の使用の意思決定に
人工知能(AI)を関与させないようにすることで合意した。
会談で両氏は、AIの活用が軍事分野でも広がっていることを受け、
核兵器の使用判断は「人間によるコントロール」を徹底し、
米中双方でAIに判断を任せないようにすることで一致した。
・石破茂首相は11/16(日本時間11/17)、訪問先のペルーで
韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領とおよそ50分間会談。
北朝鮮によるロシアへの兵派遣などを踏まえ、
ロ朝の軍事協力の進展に「深刻な懸念」を共有した。
安全保障分野で日韓、日米韓の連携を緊密にすると確認した。
両首脳はペルーで開いたアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議に合わせて面会した。
会談は10月以来2カ月連続となった。
日韓関係をこれからも安定させ、
首脳が相互往来する「シャトル外交」を活発にすると合意した。
・石破茂首相は11/16(日本時間11/17)、
トランプ米次期大統領との面会は2025年1月20日の就任式後になると明かした。
訪問先のペルーで記者団に語った。
トランプ氏側から日本政府に、就任前は各国の首脳と会わない意向が伝えられたと説明した。
・パート労働者の求人数が減少に転じた。
データ分析のナウキャスト(東京・千代田)がまとめた民間求人数の指数が
最新の10月最終週に、3年半ぶりに前年比でマイナスとなった。
人手不足が続く一方、時給の上昇で採用を断念したり、
省人化投資に振り向けたりする動きがある。
求人数の指数を業種別にみると、卸売業・小売業が前年比でマイナス10.3%と落ち込みが目立つ。
23年は9割以上伸びていた時期もあったが、24年5月以降はマイナス圏での推移が続く。
・日本や米国、中国など21カ国・地域が参加する
アジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議は11/16、ペルーの首都リマで閉幕した。
首脳宣言には「自由で開かれた貿易、投資環境を実現する」と明記した。
「米国第一」を掲げるトランプ米次期政権の発足をひかえ、保護主義に対抗する姿勢を強調。
首脳宣言では、世界貿易機関(WTO)を中核とする多角的な貿易体制を支持すると盛り込んだ。
構想から20年が経過していたAPEC加盟国・地域などによる
「アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)」の実現に向けた声明も採択した。
・トランプ次期米大統領は11/16、エネルギー長官に
石油や天然ガスの採掘会社を経営するクリス・ライト氏をあてる人事を発表。
気候変動危機の否定論者として知られ、化石燃料開発の強化を主張している。
米連邦議会の承認を得て就任すれば、
バイデン政権で強まった気候変動対策を重視する流れが反転する。
トランプ氏はライト氏が新たに設ける「国家エネルギー会議」のメンバーも務めると発表した。
エネルギー省は原油の戦略備蓄の維持などのほか、
核弾頭の保守管理、スーパーコンピューターの研究なども所管している。
・トランプ第1期政権から2023年1月まで米通商代表部(USTR)で
日本などアジア担当の代表補だったマイケル・ビーマン氏は日経新聞に対し
トランプ次期政権の貿易政策について
「ほとんどの国と貿易関係をリセットするつもりだと思う。
米国の関税を受け入れることを前提に新しい関係を築こうとしている」との見方を示した。
・サイバーエージェント <4751> [終値974.5円]
2025年3月にも薬局での受付業務を遠隔から支援するロボットのサービスを始める。
簡単な問い合わせには生成AI(人工知能)が回答し、
より詳細な説明が必要な場合はコールセンターのスタッフが対応する。
マイナ保険証への原則一本化により説明に時間のかかる薬局が増えるとみて、
負担軽減につながる新サービスを打ち出す。
・女川原子力発電所(宮城県女川町、石巻市)2号機が15日、発電と送電を始めた。
2011年に事故を起こした東京電力 <9501> [終値580.6円]福島第1原発と同じ
「沸騰水型軽水炉(BWR)」として、事故後初の稼働となる。
BWR型の原発が未稼働の状態が続き、建設だけでなく運用・保守のノウハウが先細るなか、
技術継承は綱渡りの状況が続く。
・東芝や日立製作所 <6501> [終値3951円]の原子力子会社などが出資する
BWR運転訓練センター(新潟県刈羽村)。
10月下旬、メーカーや電力会社から派遣された
10人ほどの技術者が真剣な表情で訓練に挑んでいた。
「事故の原因は何か」「甚大な事故が起きた場合、どう対処したら良いか」。
発電所と同じ装置を用い、実際に設備を動かしながら
震災後に起こりうるトラブルの対処法を学ぶ。
・原発にはBWRのほか、「加圧水型軽水炉(PWR)」と呼ばれるタイプがある。
PWRは原子炉でつくった高温高圧の水を使って、
タービンにつながる管の中の水を蒸気に変えて発電する。
原子炉の構造は複雑になるが、タービン建屋内での放射線の管理が不要となる。
一方、BWRは原子炉内の燃料棒で水を沸騰させ、その蒸気をタービンに送って発電する。
蒸気には放射性物質が含まれ、タービン建屋の放射線を管理する必要がある。
BWRの保守運用はPWRよりも難度が高い。
・女川原発の再稼働を受けて、各社で技術者の教育を本格化させている。
日立 <6501> [終値3951円]は原子炉建屋などを再現したメタバース(仮想空間)を開発。
仮想現実(VR)端末を装着すると3次元空間の360度の映像を見ながら作業手順を確認できる。
原発建設や運用保守作業を疑似体験することで技術を伝える。
日立グループの国内原子力部門の従業員数は約4000人。
国内の原発新設計画が途絶えたことで社内の建設技術は低下していくとの危機感が強い。
人工知能(AI)を用いてプラントの稼働率の向上策を提示するサービスを
電力会社に提供していく考えだ。
日立の原発担当者は「再稼働が始まることで、
ようやく新増設や建て替えに向けた議論に入れる」と期待する。
東芝は磯子エンジニアリングセンター(横浜市)に大型のスクリーンを設け、
発電所が津波に遭った場合の操作ができるシミュレーション設備を活用する。
専用設備の操作手順を学んでもらう。
原子力の新規建設を経験してきた50代以上の熟練技術者は退職する年齢を迎えつつある。
技術継承は喫緊の課題となっており、女川原発の再稼働が技術継承の第一歩となる。
・ENEOSホールディングス(HD) <5020> [終値792.2円]傘下で
資源開発を手がけるJX石油開発は、
マレーシアで1000億円超を投じて、新たな天然ガス田を掘削する。
2026年以降に生産を始める。
天然ガスの生産時に発生する二酸化炭素(CO2)を地下に埋めて、環境負荷を抑える。
ロシアによるウクライナ侵略をきっかけに
エネルギー調達を分散させることの重要性が認識された。
化石燃料から再生可能エネルギーへの置き換えが進むなかで、
石炭よりも環境負荷が小さい天然ガスの需要は高まっている。
JX石油開発は21年に英国北海での原油生産から撤退し、東南アジアに経営資源を集中している。
・第一三共 <4568> [終値4615円]ワクチンの海外輸出を目指す。
まず東南アジア市場に2030年をメドに供給を始める準備を始めた。
ワクチンは感染症の流行によって需要が左右される。
海外にも供給することで一定の生産量を確保し、
製造設備や人員配置などワクチン生産体制の維持につなげる。
・量子技術で中国の存在感が際立ってきた。
超高速の計算を可能にする「量子コンピューター」の公開特許数で、
中国が米国を逆転して1位になった。
量子技術は創薬や金融など様々な用途への活用が見込まれ、安全保障とも深く関わる。
中国勢が突出することへの警戒感は強まりそうだ。
・計算力に秀でた量子コンピューターは創薬や素材の開発など様々な産業への活用が期待できる。
一方で、国防機密などの暗号解読を容易にすることから、軍事利用の恐れも指摘されている。
公開特許は技術の開示にもつながるため、欧米ではあえて特許申請しない傾向もあるという。
米国防高等研究計画局などから補助金を受けるカナダの量子コンピューター企業、
ザナドゥのラファル・ジャニック最高執行責任者(COO)は
「特許の取得はコア技術に絞っている」と話す。
理論上、破ることができない暗号技術とされる量子暗号通信の分野では、
中国の独走が加速している。
24年8月時点の公開特許数は累計5544件で、米国の806件、日本の548件を大きく上回った。
団体別では上位10者のうち7者が中国勢だった。
・暗号通信の特許数では、日本勢も健闘する。
東芝(4位)やNEC <6701> [終値12730円](7位)は商用化に向け、
金融機関などと実証実験を進めている。
23年に英ケンブリッジに専用拠点を設置した東芝の岡田俊輔・最高デジタル責任者(CDO)は
「世界トップレベルの技術を維持している」と自負する。
米ボストン・コンサルティング・グループは量子コンピューターが
40年までに4500億~8500億ドルの経済効果を生むと予測する。
巨大市場と国家安全保障を視野に入れ、
官民学で繰り広げられる米中の主導権争いは今後、更に勢いを増すことになる。
・蚊が媒介する感染症の脅威が増している。
地球温暖化に伴い、デング熱をうつす蚊の生息域は100年で450キロメートルほど北上し、
2050年には北海道南部まで進出するとみられる。
駆除を進めても殺虫剤に耐性を持つ蚊が出現する可能性がある。
北へと移動し続ける「ヤブ蚊前線」が列島を覆う日が来るかもしれない。
様々な感染症を媒介する蚊は、地球上で最も多くのヒトを殺す生き物とされる。
「刺された後のかゆみが止まれば大丈夫」と言っていられるのは今だけかもしれない。
対策を急ぐときだ。
・知事失職に伴う兵庫県知事選が11/17に投開票され、
無所属前職の斎藤元彦氏(47)が、元同県尼崎市長の稲村和美氏(52)ら
無所属新人6人を破り、再選。
斎藤氏は自身のパワハラ疑惑などが文書で告発された問題で
県議会から全会一致で不信任決議を受け自動失職し、出直し選挙に臨んでいた。
稲村氏は混乱した県政の立て直しなどを訴え、
情勢調査などでは一時先行しているとみられたが、逆転された。
投票率は55.65%で、前回の41.1%を大きく上回った。
・厚生労働省は15日、社会保障 審議会の部会開き、会社員に扶養されるパートら
短時間労働者が厚生年金に加入する年収要件(106万円以上)を緩和する方針示した。
Posted by 占い ザ・ハーミット at
12:58
│Comments(0)